最近SNSなどで見かけるようになった「チャーハン症候群」という言葉。聞いたことありますか?名前だけ聞くとなんだかユーモラスですが、実はこれ、夏に起きやすい食中毒の俗称なんです。
私も元家政婦として、また主婦歴25年の経験から、調理後の保存や再加熱の大切さを日々感じています。この記事では、チャーハン症候群とは何か、そして家庭での予防ポイントについて、わかりやすくまとめました。
チャーハン症候群って何?

チャーハン症候群とは、加熱後のごはんなどを常温で放置していたことで発生する食中毒のこと。とくに、前の日に炊いたごはんで作ったチャーハンを、しっかり冷まさずに置いておいたり、再加熱が不十分なまま食べてしまったことで起きるケースが多いようです。
これはセレウス菌という細菌が関係しているとされていて、熱に強い芽胞(がほう)を作るため、加熱しても完全には死なず、冷却や保存が不十分だとどんどん増えてしまいます。
見た目や匂いではまったく変化がないことが多いので、「普通に食べたのに、あとから体調が悪くなった…」なんてケースも。夏は特に注意が必要です。
家庭でできるチャーハン症候群対策
私が日ごろから気をつけている、簡単だけど効果のある対策をご紹介します。
保存するごはんはすぐ冷ます
炊飯器に入れっぱなしにしたり、鍋ごと放置しておくのはNG。浅い容器に移し、できればうちわや扇風機で素早く冷まします。最近人気の解凍プレートは、冷凍した食材を早く冷ますだけでなく、調理したものの粗熱取りにもつかえます。そういった便利アイテムを使うのもひとつの手です。
残りごはんは冷凍保存が安心
冷蔵よりも冷凍のほうが、菌の増殖を抑えられて安全。私は1食分ずつラップで包んで冷凍し、必要なときに電子レンジでしっかり温めています。
再加熱は「中までアツアツ」に
特にチャーハンやピラフのような炒めごはんは、表面だけじゃなく中までしっかり加熱するのが大切。炒め直すときは、フライパンでしっかり火を通すのが安心です。
お弁当は冷ましてからフタを
熱いままフタをすると、蒸気がこもって菌が増えやすい環境に。しっかり冷ましてからフタをして、保冷グッズを使うようにしています。
チャーハンだけじゃない!気をつけたい料理たち

「チャーハン症候群」と呼ばれていますが、実際には以下のような料理でも同じリスクがあります。
- 冷ましきれずに放置されたカレーやシチュー
- 翌日再加熱したパスタやリゾット
- 大量調理した後、鍋のまま放置した煮物
つまり、「一度火を通したから大丈夫」と思って放置するのが危険。再加熱前提の料理こそ、保存と管理がカギです。余った料理を室温でそのまま放置は絶対にダメ!「二日目のカレーがおいしい」なんて言われていますが、夏はやめておいた方が安全です。
夏は「作り置き」に気をつけて
暑い季節はキッチンに立つのも大変なので、「作り置き」が便利ですよね。でも、保存方法を間違えると、せっかくの作り置きが家族の健康リスクに…。
私は作り置きする場合は、
- 小分けにして冷凍
- 必ず日付を書いておく
- 食べるときは必ず再加熱
というルールを徹底しています。
まとめ|「温度管理」が家族の安全につながる
チャーハン症候群は、誰の家庭にも起こりうる夏のリスク。でも、ちょっとした工夫と意識でしっかり防ぐことができます。
- ごはんはすぐ冷ます
- 残り物は冷凍
- 再加熱はしっかり
- お弁当には保冷対策
食材の扱い方に気をつけて、この夏もおいしく、安全に過ごしましょうね!
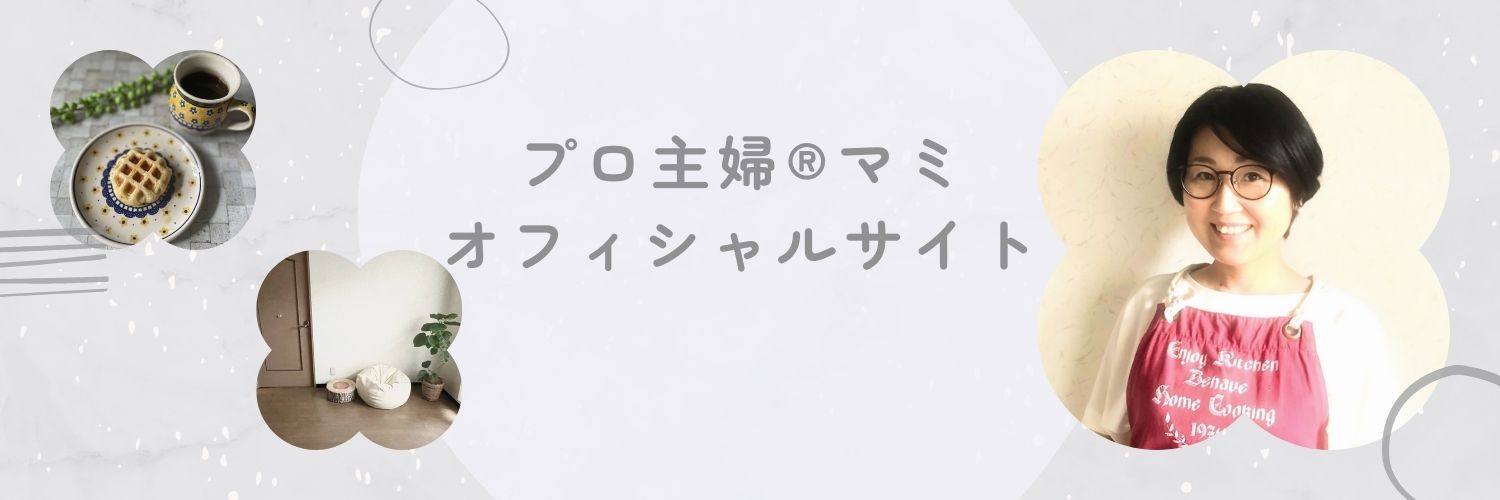

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a7c1d5d.14848f2b.4a7c1d5e.093607ef/?me_id=1353147&item_id=10000800&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmujina%2Fcabinet%2Fitem%2Fmj-1204%2Fmj-1204_top_6.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a7c1c14.7c1c784b.4a7c1c15.aa0436ed/?me_id=1339164&item_id=10000400&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fconfianceshop%2Fcabinet%2F09743146%2Fimgrc0128841207.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
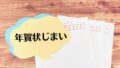






コメント